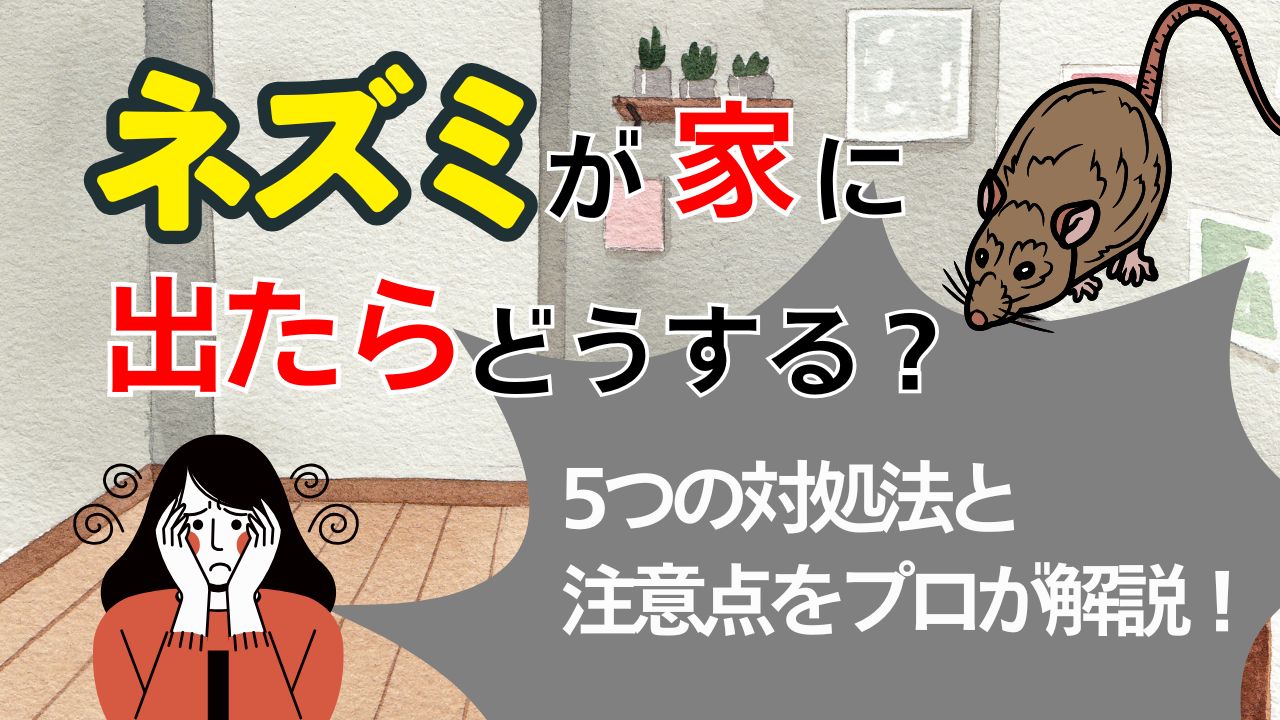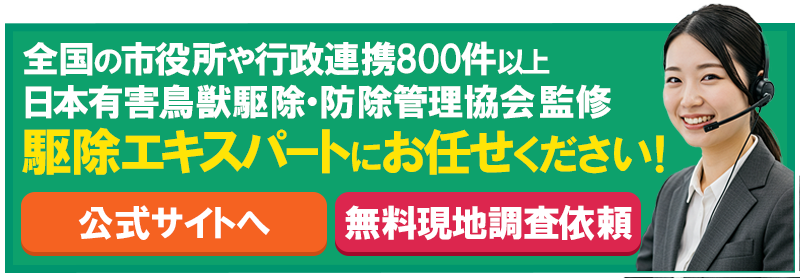「ネズミが家に出たらどうしらいい?」
そんな家に出たネズミの対処法が分からない方も多いでしょう。
ネズミは、騒音被害、食害、糞尿による悪臭、さらには感染症のリスクもあるため早急に対処すべきです。
そこで本記事では、ネズミが家に出たら早急に対処すべき理由や対処法をプロ目線で徹底解説!
また、家に出たネズミを自力で対処する際の注意点やプロの駆除業者に依頼すべき5つのケースも紹介していますのでぜひご確認ください。
「自分で対処できそうにない…」「今すぐ誰かに相談したい…」そんな場合は、プロの駆除業者に相談することも検討してみてください。
\最短即日対応!相談はこちら!! /
1. ネズミが家に出たら早急に対処すべき理由
「一匹くらいなら大丈夫かな…」
「そのうちいなくなるかも…」
そんなネズミが家に出ても放置してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、家にいるネズミは絶対に放置してはいけません!
なぜなら、放っておくと、想像以上に深刻な被害につながる可能性が高いからです。
以下にて、ネズミが家に出たら早急に対処すべき理由をを分かりやすくお伝えします。
1-1. 繫殖力が強いから被害が拡大する
ネズミは非常に繁殖力が常に強く、1年で1万匹に増えるほど急速に増えていきます。
そのため、最初は数匹しかいなくても、あっという間に家中にネズミが住み着いてしまい、被害がどんどん拡大してしまいます。
特に涼しく過ごしやすい春と秋は、ネズミの繁殖のピークと言われているため、早急に対処すべきです。
また寒さに弱いとされるネズミですが、冬の時期でも被害が拡大する傾向もあるので注意しましょう。(参考:東京都におけるねずみ・衛生害虫等相談状況調査結果)
参考:東京都保健医療局 行政担当者のための ねずみについてよくある質問&回答集
1-2. 健康をおびやかすリスクがある
ネズミは、体やフン尿にサルモネラ菌などの食中毒の原因菌といった様々な病原菌を持っています。
そのため、あなたや大切なご家族、ペットの健康が危険にさらされる危険性があります。
具体的なリスクは以下のとおりです。
- ネズミに寄生するダニやノミが家中に広がる
- アレルギーや皮膚炎を引き起こす
- キッチンを徘徊して食品を汚染する
- ダニやノミに刺される
以上のように、ネズミを放置すると様々な健康被害を引き起こすリスクがあるため、早急に対処すべきで
1-3. 家や家財をかじる
ネズミは硬い前歯で何でもかじります。
- 家の柱や壁、断熱材をかじって巣を作る
- 電気コードやガスホースをかじる
- 家具や衣類、食品をかじる
これらの修繕には、多額の費用がかかることも少なくありません。
また、ネズミがかじった電気コードやガスホース漏電から火災やガス漏れの危険性もあります。
実際、宮城県栗原市で住宅など10数軒が焼けた火事で火元となった住宅の出火原因が、ネズミが電気配線をかじったことによる漏電の可能性があることが分かっています。(参考:ネズミが配線をかじって漏電し火事に ネズミ被害の対策を聞く)
ネズミがかじる理由を知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
1-4. 精神的なストレスが大きい
今は、ネズミの被害が少なくても、日がたつにつれ「また物音がする…」「どこかに隠れているかも…」と、ネズミがいるだけで、家でリラックスできなくなり、不快感や恐怖心から大きなストレスを感じます。
また、夜中の物音で睡眠不足になることも…。
本来、安心して過ごせるはずの自宅が、落ち着かない場所になってしまうのは非常につらいですよね。
「たかがネズミ一匹」ではなく、被害が小さいうちに対処することが、結果的に時間も費用も、そして精神的な負担も少なく済みます。
そのため、ネズミの気配を感じたら、「様子を見よう」とは思わず、できるだけ早く対処することをおすすめします。
「2章」では、ネズミが家に出た時にすべき対処法を紹介しているので、ぜひご確認ください。
2. ネズミが家に出たら行うべき7つの対処法
ネズミが家に出たら、次の7つの対処法を試してみましょう。
- 忌避剤
- 粘着シート
- トラップ
- 毒餌
- 超音波機器
- 侵入口・経路の封鎖
- 清掃
以下でそれぞれ解説してまいりますのでぜひご確認ください。
ただし、ネズミの被害が広がっている場合は、自力で対処することはほぼ不可能です。
その場合は、プロの駆除業者に相談してみましょう!
プロの駆除業者は、ネズミの被害に応じて的確な対策を提案してくれます。
\最短即日対応!相談だけでも歓迎!! プロによる【無料の現地調査&お見積もり】はこちら/
2-1. 忌避剤
忌避剤はネズミが嫌がる臭いや成分を利用して、家に近寄らせないようにする、または一時的に追い払うための対処法です。
主に、ネズミが嫌がるハーブやメントール系の匂いがするスプレーを、通り道や巣がありそうな場所に吹き付けたり、設置型の忌避剤を置き対策します。
そんな忌避剤には、以下の種類があります。
- くん煙タイプ
- スプレータイプ
ただし、小さなお子様やペットがいるご家庭では、成分を確認し、影響のない安全なものを選びましょう。
お子さんやペットなどに影響がない忌避剤を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
- 手軽に試せる
- ネズミの死骸を見ずに済む
- 一時的にネズミを遠ざける効果が期待できる
- 効果は一時的で、根本的な解決にはならない
- ネズミが匂いに慣れてしまうと効果が薄れる
- 効果範囲が限られる
2-2. 粘着シート
粘着シートは、ネズミの通り道に設置し、強力な粘着力で家に出たネズミを捕獲するための罠です。
使い方は、次のようなネズミの通り道に複数設置することで、ネズミを捕獲することが期待できます。
- 壁際
- 家具の隙間
- ラットサインのある場所
またネズミの好物を置くことで、捕獲できる確率が高くなります。
ネズミの好物が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
粘着シートを使用する際は、子どもやペットが誤って触れない場所に設置してください。
万が一、くっついた場合は、食用油などでゆっくり剥がしましょう。
その他、捕獲したネズミは感染症のリスクがあるため、直接触らず、手袋やマスクを着用して処理しましょう。
処理方法は自治体のルールに従ってください。
- 比較的安価で、ホームセンターなどで手に入りやすい
- 設置が簡単
- 捕獲できたかどうか直接確認できる
- 捕獲したネズミの処理が必要で、精神的な負担が大きい
- 大型のネズミは、自力で脱出してしまうことがある
- ホコリや水で粘着力が低下しやすい
- 警戒心の強いネズミは避けて通ることがある
2-3. トラップ(捕獲カゴなど)
トラップで家に出たネズミを対処する方法では、ネズミを生きたまま、もしくは致死させて捕獲します。
使い方は、カゴの中にエサを仕掛け、ネズミの通り道に設置します。
トラップには、バネ式など様々なタイプがあるので、被害状況にあわせて選んでみましょう!
ネズミ捕獲後の処分方法は、自治体のルールに沿って行ってください。
- 繰り返し使用できるものが多い
- 生きたまま捕獲できるタイプもある
- 粘着シートより大型のネズミにも対応できる場合がある
- 警戒心の強いネズミはかかりにくい
- 設置にコツが必要な場合がある
- 捕獲後の処理が必要
2-4. 毒餌
毒餌は、ネズミに有毒な成分を含んだ餌を食べさせることで、駆除する方法です。
そんな毒餌を使用する際は、ネズミの通り道や巣の近くに設置し、ネズミに食べさせます。
ネズミ駆除に使う毒餌には、以下の種類があります。
- 即効性タイプ
- 遅効性タイプ
数日かけて効果が出る遅効性タイプだと、他のネズミに警戒されないため、警戒心の強いネズミを効果的に駆除できます。
毒餌を使用する際は、子供やペットがいるご家庭では、使用を避ける。または、鍵のかかる毒餌専用容器(ベイトボックス)を使用するなど最大限の安全対策を行いましょう。
また死骸を見つけた場合は、直接触らず、手袋・マスク着用の上で処理しましょう。
- 巣の中にいるネズミにも効果が期待できる
- 比較的安価で手に入りやすい
- 直接ネズミを見ずに駆除できる可能性がある
- 死骸が見つからないと、悪臭やウジの原因になることがある
- 子供やペットが誤って食べてしまう危険性が高い
- 毒餌を食べたネズミをペットが食べてしまうリスクがある
- 薬剤に耐性を持つスーパーラットには効かない場合がある
2-5. 超音波機器
超音波機器は、ネズミが不快に感じるとされる超音波を発生させ、ネズミを寄せ付けないようにする電子機器です。
使い方は、コンセントに差し込む、または電池を入れ、ネズミが嫌がるとされる超音波を発生させます。
いきなり超音波機器は購入できない方は、無料の超音波アプリもあるので、ぜひ試してみてください。
無料のアプリは、こちらからご確認ください。
- 設置が簡単
- 薬剤を使用しないため、安全性への懸念が少ない
- 死骸の処理が不要
- 科学的根拠が乏しく、効果が限定的
- ネズミが音に慣れてしまう可能性がある
- 壁や家具などの障害物で遮断されるため、効果範囲が狭い
- 稀に人やペットが不快感を示す場合がある
2-6. 侵入口・経路を塞ぐ
ネズミが出入りする隙間や穴を物理的に塞ぐ対処法は、家への侵入を防ぐ効果が期待できます。
家の中にいるネズミを駆除しても、外からの侵入口が開いたままでは、必ず被害が再発します。
そのため、侵入口を塞ぐことは、家に出たネズミ対策において最も重要な対処法といえるでしょう。
ただし、家の中にネズミがいる状態で、完全に塞ぐと閉じ込めてしまう可能性があります。
そのため、ある程度、駆除が進んだ段階、または駆除と並行して行いましょう。
ネズミの侵入口や経路を見つけたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
2-7. 清掃
ネズミは、餌と巣の材料を求めて家に侵入します。
これらをなくすことで、ネズミが住みにくい環境を作ることができ、侵入や再発の防止に繋がります。
そんなネズミが家に住みつきにくい環境づくりは以下のとおりです。
- 食材は密閉容器に入れる
- 食べかすを放置しない
- 蓋付きのゴミ箱を使用し、こまめに捨てる
- 巣の材料となるダンボールなどを放置せず、整理する
- 押し入れや物置も定期的に確認する
- 水回りの確認: 水漏れを放置しない
ネズミのフンや尿を清掃する時は、必ずマスクと手袋を着用し、感染症対策を行ってください。
また巣を発見した場合も、直接触らず慎重に処理しましょう。
これらの対処法を試しても、家からネズミの気配がなくならない、あるいは自分での作業に限界を感じる場合は、専門の駆除業者への相談を検討してください。
3. 家に出たネズミを自分で駆除する際の注意点
ネズミが家に出たら自分で駆除しようと考える方も多いでしょう。
しかし、手軽に見える自力での駆除には、いくつか知っておくべき注意点があります。
安易に取り組むと、時間や費用が無駄になるだけでなく、思わぬリスクに繋がることもあるので注意しましょう。
ここでは、自分で駆除する際に特に気をつけたい4つのポイントを解説します。
- 駆除効果が限られている
- 駆除できても被害が再発する
- 感染症やアレルギーなどリスクがある
- 死骸処理など精神的負担がかかる
以下でそれぞれ解説してまいります。
自力でネズミ駆除を行う方は、これらのリスクを理解した上で、対策を進めるかどうか慎重に判断しましょう。
3-1. 駆除効果が限られている
市販のグッズだけでは、家の中のネズミを完全に駆除しきれない可能性があります。
特に都市部で問題となるクマネズミは非常に警戒心が強く、賢い生き物です。
罠や毒餌を見慣れないものとして避けたり、一度危険な目に遭うと二度と近寄らなくなったりします。
また市販のグッズを置いただけでは、なかなか効果が出ないことも少なくありません。
特に近年、一部の殺鼠剤が効かない「スーパーラット」と呼ばれるネズミが増えています。
そのため、お使いの毒餌が、ご自宅にいるネズミに効果がない可能性もあります。
その他、ネズミは壁の中、天井裏、床下など、人の目が届かない場所に巣を作って繁殖します。
市販グッズは、主にネズミの「通り道」に設置するため、巣の中にいる親ネズミや多数の子ネズミまで完全に駆除するのは困難です。
目に見えるネズミを捕まえても、根本的な解決には至らないケースが多くあります。
3-2. 駆除できても被害が再発する
たとえ一時的にネズミを駆除できたとしても、侵入経路が塞がれていなければ、すぐにネズミの被害は再発してしまいます。
ネズミは、非常に体が柔らかく、わずか1.5cm程度の隙間があれば侵入できてしまいます。
また、ネズミの侵入口は多岐にわたり、素人がすべてを見つけ出して完全に塞ぐのは至難の業です。
専門家でなければ見つけられないような意外な場所から侵入しているケースも多くあるの実状です。
万が一、ネズミの侵入口や経路を見つけ、粘土や発泡スチロール、薄い板などで隙間を塞いでも、ネズミは簡単にかじって突破してしまいます。
そのため、金属製の網やパテなど、適切な材料を選んで施工する必要がありますが、知識や技術がないと、せっかく塞いだつもりでも意味がありません。
その他、ネズミは、尿などでマーキング(ラットサイン)しながら移動します。
一度、侵入経路ができた場所は、他のネズミにとっても「安全な通路」として認識されやすく、駆除しても別の個体が同じ経路から侵入してくる可能性が高いのです。
3-3. 感染症やアレルギーなどリスクがある
ネズミ本体やフン尿、寄生するダニなどを介して、健康被害を受けるリスクがあります。
ネズミはサルモネラ菌やレプトスピラ菌など、様々な病原菌を保有しているため、ネズミが徘徊したキッチンや食品、あるいはフン尿に触れることで、食中毒や感染症を引き起こす可能性があるので注意しましょう。
また、ネズミにはイエダニやノミが寄生していることが多く、ネズミが家の中を動き回ることで、これらが室内に拡散します。
イエダニに刺されると激しいかゆみや皮膚炎を起こしたり、アレルギー性喘息の原因になるリスクがあります。
特に、ネズミの死骸や巣には大量のダニが発生しやすいため注意が必要です。
フンや尿、死骸の処理、巣の撤去などの作業を行う場合は、乾燥したフンやホコリと共に病原菌やダニアレルゲンを吸い込んでしまう危険性があります。
そのため、作業時にはマスクや手袋の着用が不可欠ですが、それでもリスクをゼロにすることはできません。
特に小さなお子様や高齢者、アレルギー体質の方がいるご家庭では、より慎重な対応が求められます。
3-4. 死骸処理など精神的負担がかかる
ネズミの捕獲や駆除に伴う作業、特に死骸の処理は、精神的に大きな負担となる場合があります。
粘着シートや捕獲カゴでネズミが捕まった場合、多くは生きたまま捕獲されます。
その姿を見ることに抵抗を感じる方は少なくありません。
また、その後の殺処分や死骸の廃棄といった処理は、非常に気が重く、精神的なストレスが大きい作業です。
毒餌で駆除した場合、ネズミがどこで死ぬか分かりません。
壁の中や天井裏、家具の裏など、手の届かない場所で死骸が腐敗し、強烈な悪臭やウジが発生することがあります。
もし、死骸の場所が特定できない場合、原因特定や死骸の除去は非常に困難で、長期間にわたって不快な思いをすることになりかねません。
これらの注意点を踏まえると、自分でネズミ駆除を行うことは、必ずしも簡単かつ安全な方法とは言えないでしょう。
もし少しでも不安を感じたり、ご自身の手に負えないと感じた場合は、無理せず、専門の駆除業者に相談することを検討しましょう。
4. プロの専門業者にネズミ駆除を依頼すべきケース
「ネズミが家に出たけど、自力で対処できるの?」
「プロの駆除業者に依頼すべきケースは?」
そんな判断が難しい方も多いでしょう。
そこで、プロの専門業者にネズミ駆除を依頼すべきケースを以下にまとめました。
- ネズミの数が多く、被害が広範囲に及んでいる
- ネズミの侵入経路が特定できない
- ネズミの死骸の処理や、駆除作業に抵抗がある
- 何度駆除してもネズミが再発する
- 小さなお子さんや高齢者、ペットがいる
上記のケースに当てはまる場合、早急に対処すべきです。
ネズミは繫殖力が強いため、これ以上被害が拡大させたくない方は、今すぐプロの駆除業者に相談しましょう!
\最短即日対応!相談はこちら!! /
5. ネズミが家に出たら発生する5つの被害例と対策
ネズミが家に出たら、次の5つの被害が発生するリスクがあります。
- 騒音
- 食い荒らし
- 糞尿
- 病原体
- 繫殖
また、ネズミは上記のような被害をもたらす可能性があり、放置すると事態は悪化する一方です。
以下では、ネズミがもたらす代表的な被害とその対策について詳しく解説します。
5-1. 騒音
ネズミは夜行性のため、人々が寝静まった頃に活動が活発になります。
「天井裏で何かが走り回る音がする…」
「壁の中から聞こえるカリカリ音はなに?」
これらは、ネズミが家の中に侵入している典型的なサインです。
ネズミによる騒音被害は、以下のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。
| 影響 | 詳細 |
|---|---|
| 睡眠障害 | 継続的な騒音は、入眠困難、中途覚醒、浅い眠りなど、睡眠の質を著しく低下させます。 |
| 精神的ストレス | 騒音は、イライラ、不安感、集中力低下などを引き起こし、日常生活に支障をきたします。 |
| 健康被害 | 睡眠不足やストレスは、免疫力低下、高血圧、心臓病などのリスクを高めます。 |
特に、以下のような状況では、騒音被害がより深刻化する傾向があります。
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| 断熱材の中 | ネズミが断熱材の中に巣を作ると、音が反響し、より大きく聞こえます。 |
| 配管の近く | ネズミが配管を伝って移動すると、配管を通じて音が家中に響き渡ります。 |
| 薄い壁や天井 | 壁や天井が薄いと、ネズミの足音や鳴き声が聞こえやすくなります。 |
そんなネズミが家に出たら起こりえる騒音対策は、以下のとおりです。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| ネズミの駆除 | 騒音の根本原因であるネズミを駆除することが最優先です。 |
| 侵入経路の封鎖 | ネズミが家の中に入れないように、侵入経路を徹底的に塞ぎます。 |
| 防音対策 | 壁や天井に防音材を設置する、隙間テープで隙間を埋めるなどの対策も、一時的な効果は期待できます。(根本的な解決にはなりませんが、緊急対策としては有効です。) |
5-2. 食い荒らし
ネズミは非常に強い歯と旺盛な食欲を持つため、食品の袋や容器を簡単に食い破り、食べ物を食い荒らします。
その被害は、人間の食べ物だけでなく、以下のようなものにも及びます。
- ペットフード
- 石鹸
- 生ゴミ
- 観葉植物
- 木材
- 電気配線
- ガス管
- 衣類
- 書籍
特に注意が必要なのは、ネズミが媒介する病原菌による食中毒です。
ネズミが食品に触れることで、サルモネラ菌やレプトスピラ菌などの病原菌が食品に付着し、それを食べた人が食中毒になる可能性があります。(参考:東京都保険医療局 ねずみが与える被害)
そんなネズミが家に出たら起こりえる食い荒らし対策は、以下のとおりです。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| 食品の保管 | 食品は密閉容器に入れて保管します。 |
| 生ゴミの処理 | 生ゴミは蓋付きのゴミ箱に入れ、こまめに捨てます。 |
| 清掃 | 調理台や床に食べかすを残さないように、こまめに清掃します。 |
| ネズミの駆除 | ネズミを駆除し、食品への接触を防ぎます。 |
5-3. 糞尿
ネズミの糞尿は、非常に強い悪臭を放ちます。
特に、天井裏や床下など、換気が悪い場所に糞尿が溜まると、家中に悪臭が充満します。
さらに、ネズミの糞尿は、以下のような健康被害を引き起こす可能性があるので注意しましょう。
| 健康被害 | 詳細 |
|---|---|
| アレルギー | ネズミの糞尿に含まれるタンパク質が、アレルギー性鼻炎や喘息などの原因となることがあります。 |
| 感染症 | ネズミの糞尿には、サルモネラ菌、レプトスピラ菌、ハンタウイルスなど、様々な病原菌やウイルスが含まれています。 |
参考:厚生労働省検疫所 FORTH レプトスピラ症(ワイル病)(Leptospirosis)
糞尿の被害は、目に見えない場所で進行していることも多いため、小さなお子さんや高齢者、ペットがいるご家庭では特に注意すべきです。
そんなネズミの糞尿被害の対策は、以下のとおりです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アレルギー | ネズミの糞尿に含まれるタンパク質が、アレルギー性鼻炎や喘息などの原因となることがあります。 |
| 感染症 | ネズミの糞尿には、サルモネラ菌、レプトスピラ菌、ハンタウイルスなど、様々な病原菌やウイルスが含まれています。 |
| 清掃と消毒 | ネズミの糞尿を見つけたら、すぐに清掃し、殺菌消毒剤で消毒します。 |
| 注意 | 清掃の際は、必ずマスクとゴム手袋を着用してください。 |
| 換気 | 部屋の換気をこまめに行い、空気を入れ替えます。 |
| ネズミの駆除 | ネズミを駆除し、糞尿の発生源を断ちます。 |
| 侵入経路の封鎖 | ネズミが家の中に入れないように、侵入経路を塞ぎます。 |
5-4. 病原体
ネズミは、糞尿だけでなく、体毛や唾液、血液などにも病原体が付着している場合があります。
そのため、ネズミに直接触れるだけでなく、食品、食器、衣類などネズミが触れたものを介して、間接的に感染するリスクもあります。
ネズミが媒介する主な感染症としては、以下のようなものが挙げられます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アレルギー | ネズミの糞尿に含まれるタンパク質が、アレルギー性鼻炎や喘息などの原因となることがあります。 |
| 感染症 | ネズミの糞尿には、サルモネラ菌、レプトスピラ菌、ハンタウイルスなど、様々な病原菌やウイルスが含まれています。 |
| サルモネラ症 | 発熱、腹痛、下痢などの症状。 |
| レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛、黄疸などの症状。 |
| ハンタウイルス肺症候群 | 発熱、呼吸困難などの症状。 |
| 腎症候性出血熱 | 発熱、出血傾向、腎機能障害などの症状。 |
| 鼠咬症 | ネズミに噛まれることで感染。発熱、発疹、関節痛などの症状。 |
これらの感染症は、重症化すると命に関わる場合もあります。
そんなネズミが家に出たら起こりえる病原体対策は、以下のとおりです。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| ネズミに触らない | ネズミやネズミの死骸には、絶対に素手で触らないでください。 |
| ネズミが触れたものを消毒 | ネズミが触れた可能性のあるものは、殺菌消毒剤で消毒します。 |
| 手洗い | 外出後や食事の前など、こまめに石鹸と流水で手を洗います。 |
| ネズミの駆除 | ネズミを駆除し、病原体との接触機会を減らします。 |
| 体調不良時は医療機関へ | 発熱や体調不良などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。 |
5-5. 繁殖
ネズミは繁殖力が非常に高く、1年に数回出産し、1回に5~10匹程度の子を産みます。
1匹のネズミを見かけた時点で、すでに複数匹、あるいはさらに多くのネズミが潜んでいる可能性が高いのです。
放置すると被害が急速に拡大するため、ネズミが家に出たらすぐ対策・駆除しましょう!
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 妊娠期間 | 約20日(種類によって若干異なります) |
| 出産数 | 1回に5~10匹程度(種類や環境によって異なります) |
| 性成熟 | 生後2~3ヶ月で繁殖可能に |
そんなネズミが家に出たら起こりえる繁殖対策は、以下のとおりです。
| 対策 | 具体的な方法 |
|---|---|
| エサを与えない | ・食品は密閉容器に入れる ・生ゴミは蓋付きのゴミ箱に捨てる ・ペットフードを放置しない ・食べ残しや食べかすを放置しない |
| 巣を作らせない | ・整理整頓を心がけ、巣の材料となるものを放置しない(新聞紙、段ボール、布切れなど) ・家の周りの雑草を刈り、ネズミが隠れる場所をなくす ・定期的に清掃を行い、ネズミが巣を作りにくい環境を維持する |
| 侵入させない | ・壁や床の穴や隙間を塞ぐ(金網、パテなどを使用) ・換気口や排水口に防鼠ネットを取り付ける ・ドアや窓の隙間を塞ぐ |
6. ネズミを家に寄せ付けない対策
「ネズミが家に出たらどうしよう…」と不安に感じる方もいらっしゃいますよね。
そんなネズミを家に寄せ付けないための対策は、以下のとおりです。
- 侵入経路を徹底的に塞ぐ
- 嫌がる匂いで寄せ付けない
- 嫌がる音で撃退する
- 住み着きにくい環境を作る
- 食べ物を放置しない
- 自力で捕獲して駆除する
- 専門業者に依頼して徹底的に駆除する
上記の対処法は、効果的かつ、すぐに実行できるので、ネズミを家に寄せ付けたくない方はぜひ試してみてください。
それぞれの対策をより詳しく知りたい方は、こちらの記事からご確認ください。
【Q&A】ネズミが家に出たらどうする?【よくある疑問を解決】
ここでは、「ネズミが家に出たらどうする?」と困っている方の多くが持つ疑問点を紹介!
関連した質問も紹介しているので、ぜひご確認ください。
以下でそれぞれ回答してまいります。
Q1. 1匹だけ見かけたときは放置してもいい?
A1. いいえ、放置は厳禁です。
1匹のネズミを見かけたということは、すでに複数匹のネズミが潜んでいる可能性が高いです。
ネズミは繁殖力が非常に高いため、放置するとあっという間に数が増え、被害が拡大します。
Q2. 駆除後のネズミの死骸・糞尿はどう処理すべき?
A2. 以下の手順で処理してください。
- マスクと使い捨て手袋を着用する。
- 死骸や糞尿を、新聞紙やキッチンペーパーなどで包み、ビニール袋に入れる。
- 殺菌消毒剤(次亜塩素酸ナトリウムなど)をスプレーし、十分に浸透させる。
- ビニール袋の口をしっかりと閉じ、可燃ゴミとして廃棄する。※1
- 死骸や糞尿があった場所を、殺菌消毒剤で拭き掃除する。
- 使用したマスクや手袋、新聞紙なども、ビニール袋に入れて廃棄する。
- 作業後は、石鹸と流水で手をしっかりと洗う。
※1 自治体のルールに従って廃棄してください。
Q3. 超音波グッズは本当に効果があるの?
A3. 効果には個体差があります。
超音波グッズは、ネズミが嫌がる超音波を発して、ネズミを寄せ付けないようにするものです。
しかし、ネズミの種類や個体差、設置環境などによって効果は異なります。
また、すでに巣を作っているネズミには効果が薄い場合もあります。
そのため、超音波グッズは、他の駆除方法と併用することをおすすめします。
Q4. ネズミが家に出たらどうすればいいですか?
A4. まずは落ち着いてください。パニックになると冷静な判断ができません。
ネズミを見かけた、あるいはフンや物音などの痕跡を見つけたら、以下の対策を講じましょう!
- どこで何を見たか、どんな痕跡(フン、かじり跡、足音など)があるかを確認する
- キッチン周りの食品は、すぐに蓋付きの密閉容器に入れましょう。
- 生ゴミは蓋付きのゴミ箱に入れ、こまめに捨てましょう。
上記以外にネズミのフンを見つけた場合は、マスクと手袋をして消毒用アルコールなどで拭き取り、感染症のリスクを減らしましょう。
この記事で紹介しているような対処法から、ご自身の状況に合った方法を検討してみてください。
被害が大きい、自分で対処するのが不安、侵入口が見つからないなどの場合は、迷わずプロの駆除業者に相談しましょう。
駆除エキスパートは24時間365日受付対応しており、現地調査や見積もりは無料で行ってくれます。最短当日30分以内に自宅まで来てくれるので、ネズミの被害にお悩みの方は今すぐ問い合わせましょう。
Q5. 1匹のネズミがいたら何匹もいますか?
A5. はい、その可能性が非常に高いと言えます。
ネズミは非常に繁殖力が強く、環境が良ければあっという間に数が増えます。
そのため、ネズミを見かけたのが1匹だけでも、既に繁殖している可能性があります。
ネズミの種類にもよりますが、ネズミは群れで行動することも多いです。
また、ネズミは夜行性で警戒心も強いため、人目につくのは氷山の一角であることがほとんどです。
もちろん、ごく稀に外から迷い込んだ1匹だけのケースもゼロではありませんが、それに期待するのは危険です。
基本的には「複数いる」という前提で状況を確認し、対策を考えることが重要です。
早めに専門業者に調査を依頼すれば、被害が広がる前に正確な状況を把握できます。
当サイトがおすすめしたいネズミ駆除業者は、加盟協会累計50,000件以上の実績がある駆除エキスパートです。
害獣駆除をお考えなら駆除エキスパートの見積りをとって損はないでしょう。なぜなら、リクルートや建築・リフォーム会社が母体で「他社より安く、確実な駆除と綺麗な再発防止施工」ができる駆除業者で全国的に今人気だからです。
Q6. ネズミが家に来る理由は何ですか?
A6. ネズミが家に侵入してくる主な理由は、以下の3つです。
- 餌(エサ)がある
- 安全な隠れ家・巣作り場所がある
- 水がある
これらのが揃っていて、かつ家屋に侵入できる隙間(侵入口)があれば、ネズミは容易に入り込み、住み着いてしまいます。
逆に言えば、これらの要素をなくしていくことが、ネズミの予防・対策の基本となります。
Q7. 家に出たネズミを追い出す方法はありますか?
A7. はい、ネズミを追い払う場合、次の方法が効果的といえます。
- 忌避剤の使用
- 超音波機器の使用
- ネズミが嫌う天然素材の使用
ただし、これらの方法は、あくまでネズミを「追い払う」または「寄せ付けにくくする」ものであり、根本的な解決にはなりません。
ネズミが出て行っても、侵入口が塞がれていなければ、同じネズミが戻ってきたり、別のネズミが入ってきたりします。
そのため「追い出す」方法だけに頼るのではなく、必ず「侵入口の封鎖」と「清掃・整理整頓(ネズミが住みにくい環境づくり)」をセットで行うことが、再発を防ぐためには不可欠です。
効果が確実で根本的な解決を目指すなら、追い出すことよりも、捕獲・駆除と侵入経路封鎖を検討することをおすすめします。
まとめ|ネズミが家に出たら焦らず正しく対処しよう!
ネズミが家に出たら早急に対処しましょう!
自力で対処する場合、以下7つの方法があります。
- 忌避剤
- 粘着シート
- トラップ
- 毒餌
- 超音波機器
- 侵入口・経路の封鎖
- 清掃
ただし、ネズミの被害が広がっている場合は、自力で対処することはほぼ不可能です。
そのため、ネズミの被害が拡大している場合や自力で対処できそうにない場合は、プロの駆除業者に相談してみてください。
ネズミは繫殖力が強いため、早めに対処することをおすすめします。
これ以上被害を拡大させたくない方は、今すぐプロの駆除業者に相談しましょう!
\最短即日対応!相談はこちら!! /